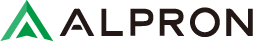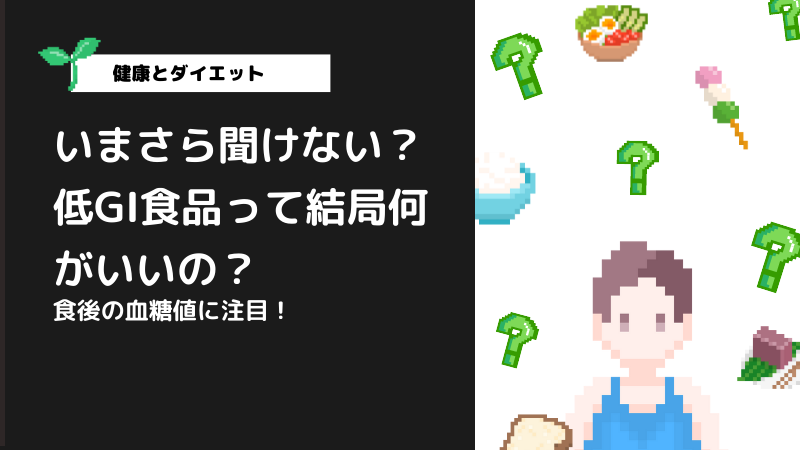筋トレと炭水化物は、切っても切り離せない関係にあります。炭水化物は筋肉を動かすための大切なエネルギー源であり、摂取量やタイミングを工夫することでトレーニング効果を大きく高められます。
一方で「筋トレ中は炭水化物を控えた方がいいのでは?」「どのくらい食べればいいの?」と迷う人も少なくありません。
この記事では、炭水化物の役割や摂取不足のリスク、トレーニング前後のおすすめ摂取法、低GI食品や高GI食品の活用方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。また、プロテインとの組み合わせ方や、秋に旬を迎える新米・旬食材の活用術もあわせて紹介。
これを読めば、筋トレ中に「いつ・どれくらい・どんな炭水化物を摂ればいいか」が理解でき、効率よく理想の体づくりを目指せるはずです。
監修者:日本プロテイン協会理事/プロテインマイスター 坂本雅俊
プロテインを始めとするスポーツニュートリション商品製造販売会社アルプロン代表取締役社長。2001年の創業以来、人々の健康と活力にあふれた毎日をサポート。2030年頃に起こるとされる世界的課題『タンパク質危機』に挑む。著作「“出世”したければ週2回筋トレすればいい」。2025年ベスト・ファーザー イエローリボン賞特別賞受賞。東京ラジオニュース(レインボータウンFM)出演中。
炭水化物とは
ここでは炭水化物の役割や基本的な特徴を解説します。
炭水化物は筋肉を動かすエネルギー源
炭水化物は、筋肉を動かすための「ガソリン」のような存在です。食事から摂った炭水化物は消化・吸収されるとブドウ糖に分解され、筋肉や肝臓に「グリコーゲン」として蓄えられます。
筋トレなどで体を動かすと、このグリコーゲンが優先的に使われてエネルギーに変わります。もし炭水化物が足りないと、体は筋肉を分解してエネルギーを作ろうとするため、筋肉量の減少につながってしまうのです。
特に高強度のトレーニングでは炭水化物の消費量が多く、回復や筋肉合成のためにも十分な摂取が必要です。炭水化物を適切に摂ることで、トレーニング効果を高め、筋肉を守ることができます。
炭水化物が不足すると起こるリスク
炭水化物が不足すると、体や脳の働きにさまざまな悪影響が出ます。代表的なものは以下の3つです。
1.脳の働きが低下する
脳はブドウ糖を主なエネルギー源としています。不足すると集中力や判断力が落ち、記憶力にも影響します。
2.強い疲労感やエネルギー不足
運動時のエネルギーが足りなくなり、疲れやすくなったり、体を動かす力が出にくくなります。また、基礎代謝も下がりやすくなります。
3.筋肉量の減少
グリコーゲンが足りないと、体は筋肉を分解してエネルギーに変えようとします。その結果、筋肉が減りやすくなります。
筋トレをサポートする炭水化物のおすすめ摂取タイミング
筋トレで炭水化物を効率よく活用するには、筋トレ前後の摂取がポイントです。ここでは、その理由を解説します。
筋トレ前
筋トレ前に炭水化物を摂っておくと、筋肉のエネルギー源である「グリコーゲン」がしっかり蓄えられ、スタミナや集中力を保ちながらパフォーマンスを高められます。
エネルギー不足のまま筋トレを行うと、疲れやすくなるだけでなく筋肉が分解されやすく、筋肥大の妨げになるのです。また、食事が足りないと低血糖で集中力が落ちたり、体調不良につながることもあります。
摂取の目安は筋トレの約2〜3時間前。米やパン、うどん、バナナなど消化の良い主食や果物を選ぶのがおすすめです。直前に食べ過ぎると消化不良を起こしやすいため、早めの補給を心がけましょう。
筋トレ後
筋トレ後は、消費された筋グリコーゲンを素早く回復させるために炭水化物を摂ることが大切です。これにより筋肉の回復力や成長を効率よく高められます。さらにタンパク質を一緒に摂ると、筋分解を抑えて合成を促進する効果が高まります。
運動直後は筋肉が栄養を取り込みやすい「ゴールデンタイム」と呼ばれるタイミング。1時間以内の摂取が理想です。おにぎりやパン、バナナなど吸収の早い炭水化物と、プロテインや低脂肪乳などのタンパク質を組み合わせるのがおすすめです。
筋トレで炭水化物を効率的に摂取するための食事の選び方
筋トレの効果を高めるには、食品の種類やGI値、トレーニング内容に合わせた摂取量を意識することが大切です。ここでは、効率よく炭水化物を取り入れるための食事の選び方を解説します。
筋トレ中の炭水化物はGI値に注目
炭水化物を選ぶときは「GI値」に注目しましょう。GI値(グリセミック・インデックス)とは、食品を食べた後の血糖値の上がりやすさを示す指標です。
| GIのランク(GI値) | 血糖値の上がり方 |
| 高GI食品(70以上) | 血糖値が急上昇しやすい |
| 中GI食品(56~69) | 緩やかに上昇 |
| 低GI食品(55以下) | ゆるやかに上昇し、安定しやすい |
数値が高いほど血糖値は上がりやすいため、日常的な食事は、なるべく低GI食品を選ぶのが基本です。
1998年にはFAO(国連食糧農業機構)とWHO(世界保健機構)も、GI値を炭水化物の代謝を評価する重要な指標とし、低GI食品の摂取を推奨しています。
筋トレ中に必要な炭水化物の摂取量
炭水化物の必要量は、トレーニングの強度や内容によって変わります。ここでは運動タイプ別に目安を紹介します。
瞬発系のトレーニング・運動の場合
短距離走や筋力トレーニング、パワー系スポーツなどの瞬発系運動では、筋肉内のグリコーゲン消費量がとても大きくなります。そのため炭水化物をしっかり補給しておくことが重要です。
摂取量の目安は体重(kg)×6g/日。例えば体重70kgなら、1日あたり約420gの炭水化物が必要とされます。ご飯やパン、麺類といった主食を中心に、果物や芋類からもバランスよく摂りましょう。
炭水化物が不足すると、体は筋肉を分解してエネルギーに変えようとするため、筋肉量の減少や回復力の低下につながります。摂取は1日の中で3食に分散するのが理想的です。
持久系のトレーニング・運動の場合
マラソンや自転車など、長時間続く持久系の運動では瞬発系よりも多くの炭水化物が必要です。目安は体重(kg)×7〜10g/日。例えば体重60kgなら420〜600g、70kgなら490〜700gが1日の摂取量の目安です。
また持久系では運動中の補給も重要です。競技時間が長ければ1時間あたり30〜60gをこまめに摂るとパフォーマンス維持に役立ちます。
十分な炭水化物補給は、筋グリコーゲンの消耗を防ぎ、筋肉分解を抑えながら長く安定したパフォーマンスを支えてくれるでしょう。
筋トレで炭水化物を摂取できるおすすめの食事
炭水化物は食品によって吸収スピードが異なり、トレーニング効果にも影響します。ここでは筋トレに役立つ食品の例を紹介します。
基本は低GI食品がおすすめ(玄米・オートミール・全粒粉パンなど)
低GI食品は消化・吸収がゆるやかで、血糖値の急激な上昇を防ぎます。日常の食事に取り入れることで、健康維持やダイエット、生活習慣病予防に役立ちます。
【主な低GI食品】
- 玄米
- オートミール
- 全粒粉パン・全粒粉パスタ
- 大豆・豆類(レンズ豆、ひよこ豆など)
- 緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリーなど)
- ナッツ類(アーモンド、くるみなど)
- 果物(りんご、ベリー類など)
【低GI食品のメリット】
- 血糖値の上昇が緩やかで、インスリンの過剰分泌を抑える
- 満腹感が長続きし、間食や食べ過ぎを防ぐ
- 糖尿病など生活習慣病のリスクを下げる
- 食物繊維が多く、腸内環境の改善に役立つ
玄米やオートミール、全粒粉パンを主食に選び、野菜や果物、ナッツを組み合わせることで、血糖値を安定させながら健康的な体づくりをサポートできます。
素早いエネルギー補給には高GI食品(白米・バナナ・和菓子など)
高GI食品は消化・吸収が早く、血糖値を急激に上げるのが特徴です。運動直前や運動中に摂取することで、短時間でエネルギーを補給でき、集中力やパフォーマンスを高めるのに役立ちます。
【主な高GI食品】
- 白米
- バナナ
- 和菓子(砂糖が多い)
- 食パン(特に白パン)
- スポーツドリンクやエネルギージェル
【高GI食品のメリット】
血糖値をすぐに上げて、素早く筋肉のエネルギー源になる
インスリン分泌を促し、筋肉への栄養取り込みをサポートする
瞬発力や集中力が必要な場面で効果的
高GI食品は「即効型のガソリン」として、トレーニング前後や運動中に取り入れると効果的です。特に短距離走やサッカーの全力ダッシュ、高強度インターバルトレーニングなど瞬発的な運動時に強い味方となります。
GI値を下げる食事の工夫
炭水化物を摂るときでも、ちょっとした工夫でGI値を下げ、血糖値の急上昇を防ぐことができます。ここでは実践しやすい工夫を紹介します。
食物繊維を一緒に摂る
炭水化物と一緒に食物繊維を摂ることで、GI値を下げ、血糖値の急上昇を防ぐことができます。特に水溶性食物繊維は糖の吸収をゆるやかにし、食後の血糖コントロールに効果的です。
【食物繊維が豊富な食品例】
- 野菜(ブロッコリー、ほうれん草など)
- 海藻(わかめ、昆布など)
- きのこ類(しいたけ、えのきなど)
- 大豆製品(納豆、豆腐など)
高GI食品を食べるときでも、野菜・海藻・きのこ・大豆製品を一緒に摂ることで、血糖値のコントロールがしやすくなります。ダイエットや生活習慣病予防にもつながるため、日常的に意識して取り入れると効果的です。
主食を最後に食べる
血糖値の急上昇を防ぐ工夫として有効なのが「主食を最後に食べる」方法です。
- 野菜・肉・魚・卵などを先に食べると、食物繊維やたんぱく質が胃の内容物に粘性を与え、糖質の吸収を遅らせる
- 血糖値の急激な上昇を防ぎ、インスリン分泌の過剰反応を抑制できる
- セカンドミール効果により、その食事だけでなく次の食事の血糖コントロールにも良い影響を与える(例:朝に野菜やオートミールを食べると、昼のご飯でも血糖値が上がりにくくなる)
普段の食事で「野菜やたんぱく質から→最後にご飯やパン」と意識するだけで、血糖値のコントロールがしやすくなります。結果として、糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防や、健康維持につながります。
ゆっくり噛んで食べる
食事のときに「ゆっくりよく噛む」ことは、血糖値の急上昇を抑えるために効果的です。
- 糖質の消化・吸収がゆるやかになり、血糖値が急に上がりにくくなる
- 噛む刺激でホルモン(GLP-1など)が分泌され、インスリンの働きを助けて血糖コントロールがしやすくなる
- 満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防止できる
1口につき20〜30回を目安に噛むことがおすすめです。無理のない範囲で意識するだけでも、食後の血糖値を安定させ、体重管理や生活習慣病予防につながります。
プロテインを併用する
食事の前後にプロテイン(たんぱく質)を取り入れることは、GI値を下げる工夫のひとつです。
【プロテインを併用する効果】
- 糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値を安定させる
- インスリンの働きを助けるホルモン(インクレチンなど)の分泌を促す
- ソイ(大豆)プロテインは腹持ちが良く、過食防止や血糖の乱高下予防にも効果的
英国ニューカッスル大学の研究では、2型糖尿病の方において、食前にホエイプロテインを摂取すると血糖コントロールが改善し、24時間の血糖値が安定しやすいと報告されています。
このように、プロテインを少し取り入れるだけで血糖値の安定や生活習慣病の予防に役立ちます。
筋トレ中の炭水化物と一緒に摂りたいおすすめプロテイン
筋トレの効果を高めるには、炭水化物と一緒にプロテインを摂ることが大切です。ここでは、目的に合わせて選べるアルプロンのおすすめプロテインを紹介します。
ALPRON WPC
「ALPRON WPC」は、筋トレ中の炭水化物と一緒に摂るのにぴったりなホエイプロテインです。タンパク質含有率は約67%で、1回(30g)あたり約20gを効率よく補給可能。糖質と組み合わせることでエネルギー回復を助け、筋合成をより効果的にサポートします。
フレーバーは14種類と豊富で、チョコやキャラメルなどの甘め系から、ヨーグルトや抹茶といったさっぱり系まで幅広く揃っています。水でもすっきり溶けやすく、泡立ちも少ないので、ゴクゴク飲みやすいのが特長です。
コスパも優秀で、900g(約30回分)は4,298円(税込/1回あたり約143円)、3kg(約100回分)は12,960円(税込/1回あたり約129円)とさらにお得。
筋トレ中の糖質補給と並行してタンパク質も取り入れたい方は、「ALPRON WPC」で効率的な栄養補給を始めてみてはいかがでしょうか。
実際に購入した方の口コミ
”溶けやすく甘さ控えめ、とても美味しいです。飽きのこない味なのでリピートします!”
”飲み心地がよく値段も手頃でリピートしています”
実際に購入した方からは「溶けやすく甘さ控えめで美味しい」「値段も手頃でリピートしている」といった口コミが多く寄せられています。味や飲み心地の満足度が高く、コスパの良さも支持されているため、継続して飲みやすいプロテインと言えるでしょう。
ALPRON SOY
「ALPRON SOY」は、植物性たんぱく質をしっかり摂れるソイプロテインです。たんぱく質含有率は約67%、1回(30g)あたり約20gのタンパク質を補給でき、炭水化物と組み合わせることで筋肉のリカバリーや合成を効率的にサポートします。大豆が原料なので乳糖不耐症の方にも安心して利用できるのが特徴です。
フレーバーは「ダブルリッチチョコレート風味」と「ストロベリー風味」の2種類。泡立ちや粉っぽさが抑えられており、まろやかな口当たりが楽しめます。ダイエット中の間食やおやつの代わりに取り入れやすいのが魅力です。
価格は900gで3,456円(税込)。1杯あたり約115円と続けやすいコスパで、定期便ならさらに14%OFFで購入できます。毎日のトレーニングをサポートする植物性プロテインとして、健康志向の方や動物性たんぱく質を控えたい方におすすめです。
実際に購入した方の口コミ
”ソイとは思えないくらい美味しいです 溶けやすくて飲みやすい 国内製造で安心ですし、すっかりハマってます”
”アルプロンのプロテインはとにかく飲みやすい!! 味も美味しいしプロテイン感がないので最高です! プロテインが苦手な私でも続けられています。”
公式ストアでは「ソイとは思えないほど美味しい」「溶けやすく飲みやすい」といった声が多く寄せられています。ソイプロテイン特有の飲みにくさがなく、国内製造で安心の品質も高評価。プロテインが苦手な方でも取り入れやすいと好評です。
ALPRON THE BUILD WPI ホエイ プロテイン
「ALPRON THE BUILD WPI」は、プロボディビルダー横川尚隆氏が監修した高品質WPI(ホエイプロテインアイソレート)です。WPCよりも不純物が少なく、1回(30g)あたり約24gのたんぱく質を素早く補給できます。
WPIは吸収スピードが非常に速く、糖質と同時に摂取することで筋肉のエネルギー補給と修復をダブルでサポート。トレーニング後に枯渇した筋グリコーゲンを炭水化物が補い、プロテインが筋合成を後押しするため、理想的なリカバリーを実現します。乳糖が少なく、胃腸への負担も少ないのが特徴です。
フレーバーはリッチチョコレート、ストロベリー&ミルク、ロイヤルミルクティー、ヨーグルト、ミックスベリーの5種類。「飲まなきゃ」ではなく「飲みたい」プロテインとしてトレーニング後のご褒美にも最適です。
価格は900g(約30回分)で7,020円(税込)。1杯あたり約234円とコスパも良好です。
筋トレの効果を最大限に引き出したい方、炭水化物との組み合わせで効率よく回復したい方におすすめのプロテインです。
実際に購入した方の口コミ
”乳糖不耐症な為、ホエイプロテインは、WPIしか飲めないから、「美味しいWPI」を割と探してました。
アルプロンさんのWPIは、元々利用させてもらってましたが、横川くんプロデュースの「THE BUILD」は、飛び抜けて美味しいです。”
公式ストアの口コミでは、乳糖不耐症の方からも「安心して飲める」「WPIの中でも特に美味しい」と高く評価されています。味の満足度が高く、WPI特有の飲みにくさを感じにくい点が支持されています。WPIでも美味しく続けたい方におすすめの一品です。
ALPRON PRO WPI プロテイン
「ALPRON PRO WPI」は、吸収スピードと純度の高さを両立したホエイプロテインです。WPCからさらに不純物を取り除き、タンパク質含有率は約80%、1食(30g)あたり約24gの高純度たんぱく質を摂取できます。
乳糖が除去されているため、乳糖不耐症の方でも安心。筋トレ中に炭水化物と組み合わせて摂ることで、エネルギー補給と筋肉修復を同時にサポートします。筋肉合成を促すロイシンも配合されており、トレーニング直後のリカバリーにも最適です。
味はダブルリッチチョコレート、フレッシュバナナ、ヨーグルト、プレーンの4種類。どのフレーバーも水だけで美味しく飲めるよう設計されており、泡立ちが少なくすっきりとした飲み口が特徴です。
価格は900gで7,020円(税込/1杯あたり約234円)、3kgで18,900円(税込/1杯あたり約189円)。コスパを重視しながらも品質にこだわったプロテインです。
筋トレで「質の高い栄養補給」を求める方に、ALPRON PRO WPIは最適な選択肢と言えるでしょう。
実際に購入した方の口コミ
”プロテインが続かない私でも、 味が美味しいので続けられそうです!!! コストパフォーマンス最強だと思います”
”シェイカーで軽く振るだけでダマにならず溶けてくれるのでストレスなく飲めるなと思いました。 少量で効果的に摂取することができるので、毎日続けやすいです。 初めてプロテインを試す方や、味や使い勝手を重視したい方には特におすすめです!”
公式ストアの口コミでは、「味が美味しくて続けやすい」「コスパが良く、ダマにならず溶けやすい」という声が多く寄せられています。味・使いやすさ・コスパのバランスが取れた商品として、日常的に筋トレをしている人やプロテイン初心者にもおすすめです。
食欲の秋に意識したい炭水化物とプロテインの摂り方
秋は新米をはじめ、美味しい食材が豊富に並ぶ季節。つい炭水化物を摂りすぎてしまいがちですが、筋トレや健康維持を考えるなら、栄養バランスを意識することが大切です。ここでは、プロテインを取り入れた上手な食べ方をご紹介します。
新米はプロテインと合わせて栄養バランスを整えるのがおすすめ
新米の季節はご飯が美味しく、つい食べ過ぎてしまいがちです。そこで役立つのがプロテイン。上手に活用すると、食べ過ぎ防止や栄養バランスの調整が可能になります。
【プロテインで食べ過ぎ防止】
ご飯を食べる前や一緒にプロテインを摂ると、たんぱく質による満腹感が得やすくなり、自然とお米の量を抑えられます。たんぱく質は消化・吸収に時間がかかるため、同じカロリーでも満足感が高く、腹持ちが良いのが特徴です。特にご飯と簡単なおかずだけの食事では、プロテインをプラスすることで食べ過ぎを防ぎやすくなります。
【栄養バランスの調整】
米中心の食事は炭水化物に偏りやすいため、プロテインでたんぱく質を補うと全体の栄養バランスが整います。肉・魚・卵などを取り入れるのが理想ですが、忙しい時や主菜が不足する時の補助としてプロテインを使うのがおすすめです。
【注意点】
プロテインも摂り過ぎればカロリーオーバーにつながります。すでにたんぱく質を十分摂れている場合は、無理に摂る必要はありません。
新米の美味しさを楽しみながら、プロテインを活用してヘルシーに食生活を整えていきましょう。
秋の旬食材は食物繊維が豊富
秋は、野菜・きのこ・芋類・果物など、食物繊維を多く含む食材が豊富に出回ります。
【代表的な秋の食材】
- さつまいも、ごぼう、れんこん、かぼちゃ
- しいたけ、しめじ、まいたけなどのきのこ類
- 柿、りんご、梨、いちじく
これらには水溶性・不溶性の食物繊維が含まれ、便通改善や血糖値の安定、コレステロール排出、満腹感による食べすぎ防止など多くの効果が期待できます。
腸内環境を整え、生活習慣病の予防にもつながるため、旬の食材を積極的に食事に取り入れるのがおすすめです。
アルプロンの米農家支援プロジェクト
アルプロンはプロテインメーカーですが、その原料は牛乳や大豆といった畜産物・農産物です。そうした背景から、アルプロンは「環境調和型農業・畜産の推進プロジェクト」を立ち上げ、農家や畜産業の環境配慮型の取り組みを支援しています。
代表的なのが、田んぼの中干し期間(水田の水を一時的に抜いて土を乾かす期間)を1週間ほど延ばすだけでメタンガスを約3割削減できる仕組み。削減分は「J-クレジット」として国に認証され、農家の新しい収入源にもなっています。環境に優しい農業を広げながら、農家の収益にも貢献する仕組みです。
さらに、この取り組みで生まれた「サステナブル備蓄米」も販売され、環境に配慮した農法で育ったお米を消費者も選べるようになっています。
アルプロンは、プロテインだけでなく“お米づくり”を通して地球環境と農業を支える挑戦も続けています。詳しい内容は公式サイトで紹介されていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
筋トレと炭水化物に関するよくある質問
筋トレと炭水化物の関係については、多くの人が疑問を抱きやすいポイントです。ここでは、よくある質問を取り上げてわかりやすく解説します。
筋トレ中の炭水化物抜きはやめるべき?
筋トレ中に炭水化物を抜くのはおすすめできません。
炭水化物は筋肉を動かす主要なエネルギー源で、不足すると本来筋肉の材料であるたんぱく質がエネルギーとして使われ、筋肉の分解につながります。
さらに、炭水化物はトレーニング中のパフォーマンスや集中力を支えるほか、筋肉の修復・合成を促すインスリンの分泌にも関わります。目安としては、無酸素運動では体重1kgあたり約6gが目安で、摂取タイミングはトレーニング2~3時間前と直後が効果的です。
極端に炭水化物を制限すると、筋肉量の減少や代謝低下、強い疲労感などを招きやすいため、バランスよく適量を摂取することが重要です。
筋トレ後は炭水化物とプロテインどちらを優先すべき?
どちらか一方ではなく、炭水化物とプロテインを同時に摂ることが最も効果的です。
炭水化物はトレーニングで消費された筋グリコーゲンを素早く回復させます。さらに、インスリン分泌を促すことで、プロテインに含まれるアミノ酸を筋肉へ効率よく届ける働きもあります。
一方、プロテイン(たんぱく質)は、筋トレで傷ついた筋繊維の修復と新しい筋肉の合成に欠かせません。
理想的なのは、トレーニング終了後1時間以内に炭水化物とたんぱく質を一緒に摂ること。食事まで時間が空くときは、手軽に摂れる補食でOKです。
【炭水化物+たんぱく質がとれる補食例】
- 肉まん
- おにぎりとチーズ
- 卵サンドイッチ
- バナナとプロテインドリンク
- フルーツヨーグルト
炭水化物:たんぱく質=約3:1を目安に、バランスよく摂ることで筋肉の回復と成長を最大限に引き出せます。
ダイエット中でも炭水化物は必要?
ダイエット中でも、炭水化物は必要です。ただし、量と質を意識して摂ることがポイント。
厚生労働省が理想としている炭水化物の割合*は、総摂取カロリーの50〜65%です。例として、1,600kcalの食事の場合、炭水化物は800〜1040kcalに相当し、約200〜260g/日が目安になります。
ダイエット時のバランスとしては、たんぱく質20〜30%、脂質20%、炭水化物50〜60%がよく使われます。
炭水化物摂取量の目安(総摂取カロリーの50〜60%の場合)
| 目標摂取カロリー | 炭水化物エネルギー量 | 炭水化物量(1g=4kcal換算) |
| 1,200kcal | 600〜720kcal | 約150〜180g |
| 1,400kcal | 700〜840kcal | 約175〜210g |
| 1,600kcal | 800〜960kcal | 約200〜240g |
| 1,800kcal | 900〜1,080kcal | 約225〜270g |
| 2,000kcal | 1,000〜1,200kcal | 約250〜300g |
これらはあくまで目安です。体重・性別・運動量・年齢などに応じて調整することが必要です。特に医師の管理下にある方や食事療法中の方は、専門家の指導を優先してください。
【炭水化物の摂り方のコツ】
- 玄米・オートミール・全粒粉パン・野菜・果物など、消化がゆるやかな炭水化物を選ぶ
- 白米や砂糖の多い製品は血糖値を急激に上げやすいため、控えめに
- 食事を数回に分散して、血糖値の急変動を避ける
炭水化物とプロテインを味方に筋トレ効果を最大化しよう!
本記事では、筋トレにおける炭水化物の役割、摂取タイミングや量、GI値に基づく食材の選び方、そしてプロテインとの賢い組み合わせ方を解説しました。
炭水化物は“筋肉を動かすガソリン”。不足すればパフォーマンスは落ち、筋分解も進みやすくなります。だからこそ、筋トレ前はエネルギーの仕込み、トレーニング後は炭水化物+プロテインで回復と合成を加速させるのが基本です。
今日から実践できる工夫は、
- 筋トレ前2〜3時間の主食(エネルギー源)を確保
- 筋トレ後60分以内に炭水化物+プロテイン
- 普段は低GI中心、必要時だけ高GIでブースト
炭水化物を正しく使えば、筋トレの成果はもっと伸びます。炭水化物×プロテインで、理想のカラダづくりを始めましょう。