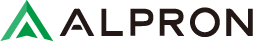「筋トレの効果をもっと加速させたい。」
「続けているのに、思うように成果が出ない…。」
そんなときに見直したいのが、プロテインの飲み方です。プロテインは、目的に合わせたタイミングや量を意識して摂ることで、筋トレ効果を大きく高めることができます。
本記事では、プロテインマイスターが、筋トレの成果を最大限に引き出すプロテインの摂り方を目的別にわかりやすく解説。タイミング・量・回数といった基本に加え、摂取不足のリスクやおすすめ食材まで幅広く紹介します。
あわせて、筋トレ中の栄養管理に役立つおすすめのプロテイン製品もご紹介。
「筋トレの成果をもっと出したい」「食事管理を見直したい」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
監修者:日本プロテイン協会理事/プロテインマイスター 坂本雅俊
プロテインを始めとするスポーツニュートリション商品製造販売会社アルプロン代表取締役社長。2001年の創業以来、人々の健康と活力にあふれた毎日をサポート。2030年頃に起こるとされる世界的課題『タンパク質危機』に挑む。著作「“出世”したければ週2回筋トレすればいい」。2025年ベスト・ファーザー イエローリボン賞特別賞受賞。東京ラジオニュース(レインボータウンFM)出演中。
筋トレに必要な1日のタンパク質の摂取量
筋トレの効果を高めるためには、1日にどれくらいのタンパク質を摂るべきかを知っておくことが大切です。1日に必要なタンパク質量は運動習慣によって変わります。
以下の計算式を使えば、自分にとって最適な摂取量を導き出せます。
【タンパク質の必要量を求める計算式】
体重(kg) × 運動量 = 1日に必要なタンパク質量(g)
運動量の目安は次のとおりです。
| 運動習慣 | 目安 |
| 運動をしていない人 | 体重× 0.8〜1.0g |
| 軽い運動をしている人 | 体重× 1.2〜1.5g |
| 筋肉をつけたい人 | 体重× 2.0g |
例)体重60kgで軽い運動をしている場合
60kg × 1.2〜1.5g = 72〜90g
この場合、1日に必要なタンパク質量は約72g〜90gとなります。ご自身の体重と運動量をあてはめて、自分に必要なタンパク質の目安を把握しましょう。
タンパク質が不足することによるリスク
タンパク質は筋肉の材料となるだけでなく、身体づくりや回復、日々のパフォーマンス維持にも欠かせない栄養素。不足した状態が続くと、身体にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。
特に注意したいのは次のようなリスクです。
- 筋肉量の減少・筋力低下
- パフォーマンスの低下
- 疲労感の増加
それぞれ、どのような影響があるのか詳しく見ていきましょう。
筋肉量の減少、筋力低下
タンパク質が不足すると、筋肉量が減り、筋力も低下しやすくなります。筋肉は主にタンパク質でできており、身体のなかで最も多くのタンパク質を含む組織です。
筋肉は、日々、分解と合成をくり返していますが、十分にタンパク質をとらないと、このバランスがくずれ、筋肉を維持・再生することができなくなります。
また、身体は生命維持に欠かせない臓器や機能を優先するため、タンパク質が足りないと、筋肉からタンパク質を取り出して使おうとします。その結果、筋肉が分解され、筋肉量が減少。筋力も弱くなってしまうのです。
さらに、筋肉が減ると基礎代謝が下がり、太りやすくなる、体温が下がる、免疫力が落ちるといった健康への悪影響も出てきます。
パフォーマンス低下
タンパク質が不足すると、身体や心のパフォーマンスが低下してしまいます。まず、筋肉の主成分であるタンパク質が足りないと、筋肉の修復や維持ができなくなり、筋力が低下します。これにより、運動時のパワーや日常生活での動きが鈍くなってしまうのです。
さらに、集中力ややる気にも影響します。脳の神経伝達物質(ドーパミンやセロトニンなど)は、タンパク質から作られるため、不足すると思考力が落ちたり、ぼんやりしやすくなったりすると言われています。
また、ホルモンや免疫機能もタンパク質から作られているため、足りない状態が続くと体調を崩しやすくなり、回復力も下がります。
このように、タンパク質不足は「動けない」「考えがまとまらない」「やる気が出ない」といった、心身両面のパフォーマンスを下げてしまうのです。
疲労感の増加
タンパク質が不足すると、「なんだかいつも疲れている…」という状態が続きやすくなります。その理由のひとつが、身体の修復力の低下です。
筋肉や血管、臓器などの細胞は日々ダメージを受けていますが、タンパク質が不足していると、こうしたダメージを修復・再生する力が弱まり、疲労が蓄積されやすくなります。
また、やる気や気分をコントロールする「ドーパミン」や「セロトニン」などの神経伝達物質は、タンパク質からつくられます。これらが不足すると、だるさ・眠気・精神的な疲労感が出やすくなるのです。
さらに、貧血のリスクも見逃せません。ヘモグロビン(酸素を運ぶ成分)をつくる材料にもタンパク質が必要です。不足すると酸素の運搬がうまくいかず、「身体が重い」「すぐ息切れする」といった疲れにつながります。
加えて、タンパク質不足はエネルギー代謝にも関わり、ビタミンやミネラルの吸収・働きにも影響を与えます。こうした要素が重なることで、慢性的な疲労感を引き起こすのです。
「最近ずっと疲れやすい…」と感じる方は、もしかするとタンパク質が足りていないのかもしれません。
タンパク質を効率的に吸収するポイント
タンパク質を効率よく身体に取り入れるには、摂取するタイミングや組み合わせる栄養素にも工夫が必要です。
- 3食に分けてバランスよく摂取する
- 他の栄養素も合わせて摂取する
- アミノ酸スコアも意識する
ここでは、日々の食事の中でタンパク質をしっかり活かすためのポイントを解説します。
3食に分けてバランスよく摂取する
タンパク質は、一度にたくさん摂ればよいというものではありません。1回の食事で身体が吸収できるタンパク質の量は、およそ40〜50g程度といわれています。それ以上に摂取しても、使いきれなかった分は体外に排出されたり、エネルギーとして使われたりしてしまいます。
また、筋肉は空腹の時間が長く続くと分解されやすくなります。つまり、タンパク質をこまめに安定して補給することが、筋肉の維持や合成にとって効果的なのです。
タンパク質は炭水化物や脂質のように体内に長く蓄えておけない栄養素です。だからこそ、1日のなかで偏りなく3食に分けて摂取することが、効率の良い活用につながります。
他の栄養素も合わせて摂取する
タンパク質をしっかり摂ることは大切ですが、その働きをサポートする栄養素も一緒にとることで、より効率よく吸収されます。
とくに注目したいのが、タンパク質の代謝や合成を助けるビタミンB6や、エネルギー源として働く炭水化物です。それぞれの栄養素がどのようにタンパク質の吸収を助けてくれるのか、詳しく見ていきましょう。
ビタミンB6
ビタミンB6は、タンパク質の代謝(分解・合成)を助ける重要な栄養素です。食事からとったタンパク質は、消化酵素によってアミノ酸に分解され、小腸から吸収されます。この分解や再利用の流れにビタミンB6が欠かせません。
また、体内ではアミノ酸からタンパク質を再合成する働きもあり、その過程でもビタミンB6が「補酵素」として酵素をサポートします。そのため、ビタミンB6が十分にあることで、タンパク質を効率よく活用できるのです。
タンパク質を多くとる人ほどビタミンB6の必要量も増えるため、不足しないよう意識して補いましょう。かつお、まぐろ、鶏ささみ、バナナ、さつまいも、アボカドなどに豊富に含まれているので、日々の食事に取り入れるのがおすすめです。
炭水化物
炭水化物は身体の主要なエネルギー源。不足するとエネルギーが足りなくなり、筋肉や体内のタンパク質を分解してエネルギーとして使おうとする働き(糖新生)が起きます。
しっかり炭水化物をとることで、タンパク質を身体づくりに優先的に使えるようになり、筋肉の維持や回復がスムーズになるのです。
また、炭水化物を摂取すると分泌されるインスリンには、筋肉へのアミノ酸の取り込みを促す働きがあり、筋タンパク質の合成をサポートしてくれます。さらに、筋肉に蓄えられるグリコーゲンが保たれることで、筋肉の分解を防ぐ効果も期待できます。
炭水化物は、白米、玄米、さつまいも、オートミール、バナナ、全粒粉パンなどに多く含まれているので、毎日の食事で意識的に取り入れるのがおすすめです。
アミノ酸スコアも意識する
タンパク質の「量」だけでなく、「質」も意識することが大切です。その質を判断する目安が、アミノ酸スコアです。
アミノ酸スコアは、体内で作ることができない”必須アミノ酸”のバランスを示した指標で、スコアが高いほど身体にとって効率よく使える良質なタンパク質とされています。
必須アミノ酸のどれかが不足していると、他の成分が足りていても、タンパク質として十分に活用されません。つまり、アミノ酸スコアの低い食品ばかりを食べていると、一部がうまく使われずに無駄になってしまう可能性があるのです。
ただし、アミノ酸スコアが低めの食材でも、ほかの食品と組み合わせることで補い合うことができ、全体のバランスを整えられます。
アミノ酸スコアを意識して食材を選ぶことで、摂取したタンパク質を最大限に活かすことができます。
タンパク質が豊富な食材
タンパク質をしっかり摂るためには、どんな食材に多く含まれているかを知っておくことが大切です。ここでは、タンパク質が豊富な食材と、それぞれの含有量(100gあたり)を紹介します。
※タンパク質量は文部科学省「食品成分データベース」(2025年7月時点)をもとに編集しています。一部、わかりやすさのために食品名を簡略化しています。
肉類
肉類はタンパク質の宝庫で、とくに鶏むね肉やヒレ肉は脂質が少なく、効率よくタンパク質をとれる食材です。日々の食事に取り入れやすく、筋肉の維持・増強を目指す方におすすめです。
| 食品名 | タンパク質量(g)/100g |
| 豚/ヒレ/赤肉(焼き) | 39.3 |
| 鶏/むね/皮なし(焼き) | 38.8 |
| 鶏/ささみ(ソテー) | 36.1 |
| 豚/もも/皮下脂肪なし(焼き) | 30.2 |
| 牛/もも/皮下脂肪なし(ゆで) | 30.0 |
魚介類
魚介類は高タンパク・低脂肪なものが多く、DHAやEPAなどの良質な脂も同時にとれるのが特徴。焼き魚や刺身など、調理法を工夫することでヘルシーに栄養を摂取できます。
| 食品名 | タンパク質量(g)/100g |
| クロマグロ/赤身(生) | 26.4 |
| 塩サバ | 26.2 |
| ブリ(焼き) | 26.2 |
| カツオ(生) | 25.8 |
| マイワシ(焼き) | 25.3 |
| サケ/皮つき(ソテー) | 25.2 |
卵
卵はアミノ酸バランスが優れた“完全栄養食品”といわれ、手軽に食べられる優秀なタンパク源です。調理法によって風味も変わるので、飽きずに続けられるのも魅力です。
| 食品名 | タンパク質量(g)/100g |
| 鶏卵/卵黄(生) | 16.5 |
| 鶏卵/全卵(目玉焼き) | 14.8 |
| 鶏卵/全卵(炒り) | 13.3 |
| うずら卵/全卵(生) | 12.6 |
大豆製品
大豆製品は植物性タンパク質が豊富で、肉や魚に頼らずにタンパク質を補える貴重な存在。
納豆や豆腐、きな粉など、毎日の食事に取り入れやすい食材がそろっています。
| 食品名 | タンパク質量(g)/100g |
| きな粉/黄大豆/脱皮大豆 | 37.5 |
| 油揚げ/油抜き(焼き) | 24.9 |
| 糸引き納豆 | 16.5 |
| 湯葉/干し(湯戻し) | 15.7 |
| 絹ごし豆腐 | 5.3 |
牛乳
牛乳はタンパク質だけでなく、カルシウムやビタミンも同時にとれる栄養価の高い飲み物です。脱脂粉乳はタンパク質が特に豊富で、手軽な補給源として活用できます。
| 食品名 | タンパク質量(g)/100g |
| 脱脂粉乳 | 34.0 |
| 普通牛乳 | 3.3 |
食事だけで足りない場合はプロテインがおすすめ
理想は毎日の食事からしっかりとタンパク質を摂ることですが、忙しい日が続いたり、食が細い方、運動量が多い方にとっては、必要量を毎日きちんと摂取するのは意外と難しいものです。
そんなときに便利なのが、飲み物として手軽に摂れるプロテイン。水や牛乳に溶かしてすぐに飲めるので、朝食の一品や間食代わりとしても取り入れやすいのがメリットです。
プロテインにはいくつかの種類があり、それぞれ原料やタンパク質量が異なります。以下は、代表的な種類とタンパク質量の目安です。
| 種類 | 原料 | タンパク質量の目安 |
| WPC(ホエイプロテインコンセントレート) | 牛乳 | 約20g(1食30g程度) |
| WPI(ホエイプロテインアイソレート) | 牛乳 | 約24g(1食30g程度) |
| ソイプロテイン | 大豆 | 約20g(1食30g程度) |
※タンパク質量はアルプロンの商品を参考にしています。
タンパク質をしっかり摂取できるおすすめプロテイン
プロテインを選ぶ際は、目的や体質、飲みやすさなどを基準に、自分に合ったものを選ぶことが大切です。ここでは、アルプロンのプロテインのなかから、タイプ別におすすめ商品をご紹介します。
それぞれの特徴と、実際に購入された方の口コミもあわせて参考にしてください。
ALPRON WPC
ALPRON WPCは、筋トレに必要なタンパク質を最も効率的に摂取できるホエイプロテインです。
1回(30g)あたり約20gのタンパク質が含まれており、吸収スピードが速いホエイプロテインだからこそ、トレーニング後のゴールデンタイムにしっかり届きます。タンパク質含有率は約67%と高水準で、筋肉の合成をしっかりサポート。
価格は、900g(約30回分)で税込4,298円(1回あたり約143円)と、WPCとしては非常に高いコストパフォーマンスを実現しています。また、3kgパック(約100回分)は12,960円(税込)で、1回あたり約129円とお得です。
さらに定期便を利用すれば、通常価格から15%OFFになるため、継続して飲みたい方には特におすすめです。
全10種の豊富なフレーバーで、甘めからさっぱり系まで好みに合わせて選択可能。溶けやすくダマになりにくいので、筋トレ後でもサラッと飲めるもの続けやすいポイントです。
コスパも味も妥協したくない方はもちろん、日々の筋トレ効果をしっかり引き出したい方にもおすすめのプロテインです。
実際に購入した方の口コミ
”色んなプロテインを試したことがありますが、こちらのフレーバーはさわやかな酸味とほどよい甘さがあり毎日でも飽きがこない! トレーニング後と食感に摂取しています。 競技のパフォーマンス向上と健康のためには良い商品だと思いました。”
”飲み心地がよく値段も手頃でリピートしています”
公式ストアのレビューでは、飲みやすさや味の飽きにくさ、価格のバランスを評価する声が多く見られます。トレーニング後の補給にちょうどよく、継続しやすいプロテインとして愛用している方が多いようです。
ALPRON SOY
ALPRON SOYは、筋トレ中のタンパク質補給をヘルシーに続けたい方におすすめののソイプロテインです。
タンパク質含有率は約67%で、1回(30g)あたり約20gのタンパク質をしっかり補給可能。
価格は900gで約3,450円(税込)、1回あたり約115円とコスパにも優れています。
フレーバーは、ストロベリーとダブルリッチチョコレートの2種類。ソイプロテインにありがちな粉っぽさやクセが少なく、泡立ちも控えめで飲みやすい仕上がりになっています。
また、乳糖を含まないため、ホエイプロテインでお腹がゆるくなりやすい方や、乳製品を避けたい方にも安心。間食や朝食代わり、減量中の栄養サポートとしても活用しやすく、食事の置き換えにも適しています。
さらに、定期便を利用すれば14%OFFで購入できるため、トレーニングを継続する方にも無理なく取り入れやすい1杯です。
ALPRON SOYは、ホエイが合わない方や、植物性で効率よくたんぱく質を摂りたい方に選んでほしいソイプロテインです。
実際に購入した方の口コミ
”ソイとは思えないくらい美味しいです 溶けやすくて飲みやすい 国内製造で安心ですし、すっかりハマってます”
”水にすぐ溶けるので、トレーニング後のシェイクもしんどく無くて最高です! 美味しいので、乳糖不耐症の味方すぎました”
Amazonレビューでは、味の飲みやすさや溶けやすさ、乳糖不使用の安心感が高く評価されています。「ソイなのに美味しい」「お腹にやさしい」など、無理なく続けられるプロテインとして好評を得ています。
ALPRON THE BUILD WPI ホエイ プロテイン
ALPRON THE BUILD WPIは、筋トレ効果を最大限に引き出したい中上級者のために開発された、高品質なWPIホエイプロテインです。
監修は、フィジークやボディビル競技で日本一に輝いたプロボディビルダー・横川尚隆さん。自身の経験から、「お金がなくても理想の身体をつくり続けられるプロテインを」との思いで、“高品質・低価格・うまさ”の3つを兼ね備えた製品として誕生しました。
WPI製法により、不純物や乳糖を徹底的に除去しているため、たんぱく質含有率は約80%と高純度。1回(30g)あたり約24gのたんぱく質を効率よく補給でき、乳糖でお腹を下しやすい方でも安心して摂取できます。
価格は900gで税込7,020円(1回あたり約234円)と、WPIとしては良心的な価格設定も魅力。
フレーバーはロイヤルミルクティー、リッチチョコレート、ストロベリー&ミルク、ヨーグルト、ミックスベリーの5種類をラインナップ。味にもこだわっており、「飲まなきゃ」ではなく「飲みたい」と感じられる美味しさが追求されています。
引き締まった身体を目指す方はもちろん、プロレベルのボディメイクを目指す中級〜上級者にもおすすめできるWPIプロテインです。
実際に購入した方の口コミ
”乳糖不耐症な為、ホエイプロテインは、WPIしか飲めないから、「美味しいWPI」を探してました。
アルプロンさんのWPIは、元々利用させてもらってましたが、横川くんプロデュースの「THE BUILD」は、飛び抜けて美味しいです。ロイヤルミルクティー味を試させてもらいましたが、リッチチョコも次は飲んでみたいです。”
”横川尚隆さんが監修しているプロテインなので、以前から気になって購入しました。
リッチチョコレートの味はミルクチョコレートみたいでとても美味しかったです!”
公式レビューでは、「WPIなのに美味しい!」という驚きの声や、横川さん監修による安心感・信頼感が多く寄せられています。乳糖不耐症の方にも飲みやすく、継続したトレーニングのモチベーションを高めてくれる一杯として支持されています。
ALPRON PRO WPI プロテイン
ALPRON PRO WPIは、タンパク質の質にこだわる筋トレ中上級者のためのハイスペックなWPIプロテインです。
WPI(ホエイプロテインアイソレート)製法により、不純物や乳糖をほとんど取り除き、タンパク質含有率は約80%。1回(30g)あたり約24gのタンパク質をスピーディーに補給し、トレーニング直後のリカバリーや筋肥大を効率的にサポートします。
価格は900gで税込7,020円(1回あたり約234円)、お得な3kgパックでは税込18,900円(1回あたり約189円)と、容量が増えるほどコスパも向上。さらに定期便を利用すれば15%OFFとなり、本気で身体づくりに取り組む方の継続使用にも最適です。
また、乳糖不耐症の方でも安心して飲めるWPI製法で、必須アミノ酸「ロイシン」も配合。筋肉の合成刺激をさらに高める配合設計となっています。
ハードなトレーニングを日々積み重ねている方や、タンパク質摂取の質を高めたい方にこそ選んでほしい、プロ仕様の一杯です。
実際に購入した方の口コミ
”プロテインが続かない私でも、 味が美味しいので続けられそうです!!! コストパフォーマンス最強だと思います”
”パッケージも改良されて扱いやすくなり、WPI特有の臭みも抑えられてました!”
Amazonレビューでは、味の飲みやすさやコストパフォーマンスの高さに加え、ユーザー目線での改良や品質向上が評価されています。プロテインに苦手意識がある方でも「これなら続けられる」と感じる、高品質かつ実用的なWPIプロテインとして支持されています。
タンパク質を効率的に吸収できるプロテインを飲むおすすめタイミング
プロテインは、目的に合わせて「いつ飲むか」を意識することで、タンパク質の吸収効率が高まり、より効果的に身体づくりをサポートできます。
ここでは、プロテインの効果を最大限に引き出すためのおすすめのタイミングと、筋肥大やダイエットなど目的別の摂取ポイントをわかりやすく解説します。
プロテインの効果を最大化させる4つのタイミング
プロテインの効果を最大化させるためには、次の摂取タイミングで摂取することをおすすめします。
・朝食時
・トレーニング1時間前
・筋トレ直後
・就寝前
それぞれどのようなメリットがあるのか、確認してみましょう。
1.朝食時
就寝中は食事ができない状態が長く続くため、起床時は体内のエネルギー量が少なくなっています。朝食を食べずにエネルギー不足のまま活動を始めてしまうと、筋肉の分解が進み、体づくりに悪影響を与えます。
朝食の重要性は理解しているけど、「朝食を準備したり、食べている時間がない…」、「朝は食欲がわかない…」という人も多いはず。そんな人は積極的にプロテインを活用してみましょう。
溶かすだけですぐに飲める上、液体のプロテインは食欲がなくても摂取しやすいため、忙しい朝の時間にうってつけです。
朝からしっかりとタンパク質を摂取することで、体づくりの効果が高まるという研究報告もあります。普段からしっかり朝食を食べている人でも、プロテインを付け加えることで体づくりを効果的に進めることができるでしょう。
2.トレーニング1時間前
筋肉は日々、分解と合成を繰り返しています。タンパク質はアミノ酸まで分解されてから小腸から吸収され、血液に流れます。血液中のアミノ酸の濃度を「血中アミノ酸濃度」といい、プロテインを飲むことで血中アミノ酸濃度は高まります。
血中アミノ酸濃度が高まると、筋肉の分解が抑制されて、合成が促進されます。つまり、筋肉が成長しやすくなります。
そのため、筋肉の分解と合成が活発になる筋トレ中〜直後に、血中アミノ酸濃度を高めておくのが理想です。
ホエイプロテインは飲んでから血中アミノ酸がピークになるまで1〜2時間かかります。そのため、筋トレの1時間前から飲み始めておくと、血中アミノ酸濃度が高い状態で筋トレを行えます。
3.筋トレ直後
筋トレ直後のプロテイン摂取も、プロテインの効果を最大限に引き出すタイミングの一つです。
筋トレ直後は、筋肉の合成を促す成長ホルモンやインスリンの分泌が活発になり、筋肉づくりのための栄養補給に絶好のタイミングです。
筋肉の分解が早い高齢者を対象にした研究では、「筋トレ後30分以内にプロテインを摂取」「筋トレ後2時間後にプロテインを摂取」で比較すると、効果の差は大きく、2時間後に摂取した場合、筋肉合成の効果が低下してしまうという結果もあります。
また、筋トレによってエネルギー不足となった身体のまま活動を続けてしまうと、筋肉の分解が進んだり、疲労回復に時間がかかってしまいます。筋トレ直後はプロテインなどを活用して、速やかに影響補給を行いましょう。
4.就寝前
就寝後1時間ほどで成長ホルモンの分泌はピークを迎えます。成長ホルモンが分泌されていると、筋肉も合成されやすいので、このタイミングで血中アミノ酸濃度をあげておくと効果的です。
就寝直前に飲めば、ちょうど就寝1時間後に血中アミノ酸濃度を高められます。しかし、夜におしっこに行きたくなる可能性があります。
就寝前にプロテインを摂取するなら、プロテインの特徴を活用するとさらに効果的です。就寝前は、ゆっくりと吸収されるソイプロテインやカゼインプロテインがおすすめです。
目的別のプロテイン摂取タイミング
プロテインをいつ飲むかは、「どんな目的で身体づくりをしているか」によって最適なタイミングが異なります。
ここでは、筋肥大を目指す場合と、ダイエットを目的とする場合に分けて、摂取のベストタイミングをご紹介します。
筋肥大は食後
タンパク質には食欲を抑制する働きがあるといわれています。筋肥大のためには、十分なカロリー摂取が必要ですが、食前にプロテインを飲んで食欲が落ちてしまうと、食事量が落ちてしまう可能性があります。
そのため、筋肥大が目的の場合は、しっかり食事を食べてから、プロテインを飲みましょう。
ダイエットは食前
ダイエット目的のときは、食前に飲みましょう。タンパク質の食欲を抑制する働きによって、楽に食事制限できるようになります。
食前にプロテインを飲んで、タンパク質を満たし、カロリー摂取を抑えましょう。
タンパク質摂取の効率を上げるおすすめのプロテインを飲む回数
プロテインは、1日3回を目安に、こまめに摂取することをおすすめします。というのも、人が一度に吸収できるタンパク質量には限界があり、およそ40〜50g程度といわれています。
そのため、一度に大量に飲むよりも、朝・運動後・就寝前などに分けて摂取する方が、血中のアミノ酸濃度を安定して保ちやすく、筋肉の合成効率が高まるのです。
大切なのは、必要なタンパク質量を理解し、適切なタイミングと回数で摂ること。自分の目標やライフスタイルに合わせて、無理なく継続できる飲み方を心がけましょう。
プロテインの飲み方に関するよくある質問
ここでは、プロテイン初心者から筋トレ経験者まで多くの方が気になる“よくある質問”をQ&A形式で解説します。
プロテインを摂り過ぎるとどうなる?
プロテインは身体づくりに役立つ反面、摂りすぎると身体に負担がかかることがあります。
主なリスクとしては、以下のようなものが考えられます。
- 体重増加
- お腹の不調(下痢・便秘など)
- 体臭・おならのにおい
- 腎臓や肝臓への負担
- むくみ・肌荒れ、疲れやすさ
特に体重1kgあたり2g以上のタンパク質は負担が大きくなる可能性も。必要量を守って、無理なく続けることが大切です。
プロテインは水よりも牛乳で飲んだ方が良い?太るというのは本当?
基本的には水で飲むのがおすすめです。牛乳でプロテインを飲むと、牛乳に含まれるタンパク質やカルシウム、ビタミンなどの栄養素も一緒にとれるというメリットがあります。
一方で、脂質や糖質も含まれるため、摂取カロリーは水に比べて高めになります。ダイエット中の方や、太るのが気になる方には不向きかもしれません。
また、牛乳は胃にたまりやすいため、筋トレ前後などのタイミングでは、消化に時間がかかり身体が重く感じることもあります。
水で飲む場合は、カロリーがゼロで胃腸にも負担がかかりにくく、溶けやすいのもメリットです。プロテイン本来の味をしっかり楽しみたい方にも水での摂取がおすすめです。
寝る前にプロテインを飲むと効果的?何時間前が良いのか?
就寝後1時間ほどで成長ホルモンの分泌はピークを迎えます。成長ホルモンが分泌されていると、筋肉も合成されやすいので、このタイミングで血中アミノ酸濃度をあげておくと効果的です。
就寝直前に飲めば、ちょうど就寝1時間後に血中アミノ酸濃度を高められます。しかし、夜におしっこに行きたくなる可能性があります。
プロテインは毎日飲んでも大丈夫?
健康な人であれば、適量を守れば毎日飲んでも問題ありません。
ただし、プロテインはあくまでタンパク質を補うためのサプリメントです。基本は食事からタンパク質をとり、足りない分を補助的に摂取するのが理想的です。
毎日飲む場合の注意点は以下の通りです。
- 過剰摂取はNG(体重×0.8~2.0gが目安)
- 運動量や体格に応じた量を意識する
- 腎臓や肝臓に持病がある方、妊娠中・授乳中の方は医師に相談
バランスの良い食事を基本に、無理のない範囲で取り入れることが大切です。
筋トレがない日はプロテインを飲まないほうがいい?
筋トレがない日でもプロテインを飲んでOKです。筋肉はトレーニング後の休養日にこそ回復・成長します。そのため、タンパク質の摂取は休養日も重要。筋肉の維持や代謝をサポートするには、毎日安定して一定量のタンパク質を摂ることが大切です。
ただし、食事でしっかりタンパク質がとれていれば、プロテインは飲まなくてもかまいません。あくまで「足りないときの補助」として、目標量に合わせて調整しましょう。
プロテインは、タイミング・量・回数がカギ!正しく飲んで筋トレ効果を最大化しよう
本記事では、筋トレの効果を高めるためのプロテインの飲み方や活用法について解説しました。
タンパク質の摂取量の目安は以下の通りです。
- 運動していない人:体重×0.8〜1.0g
- 軽く運動している人:体重×1.2〜1.5g
- 筋肉をつけたい人:体重×2.0g
普段の食事で足りない分を、プロテインで効率よく補いましょう。飲むタイミングは、トレーニングの1時間前・直後・就寝前が効果的です。1度にまとめて摂るよりも、数回に分けてこまめに摂取するのがポイント。
タンパク質の摂取量とタイミングを意識することで、筋トレの成果を高め、理想の身体に近づけます。プロテインを上手に活用して、効率よくボディメイクを進めましょう!